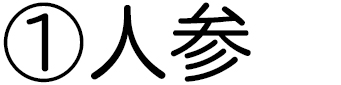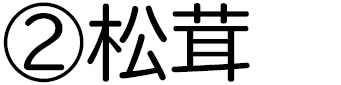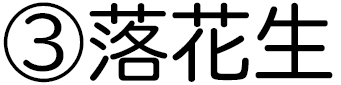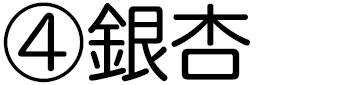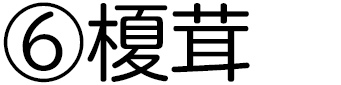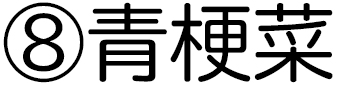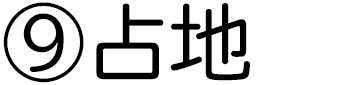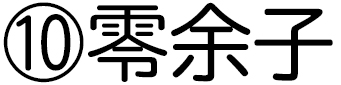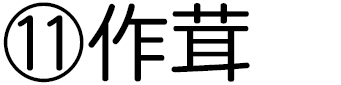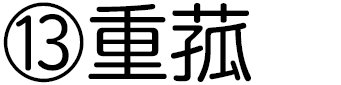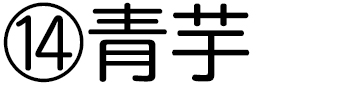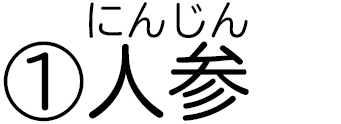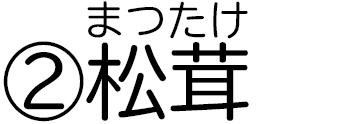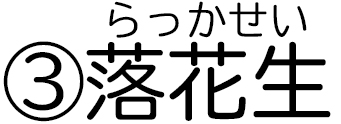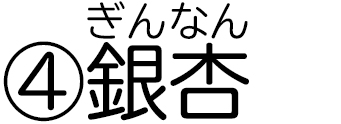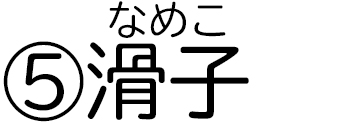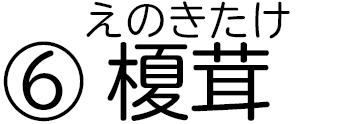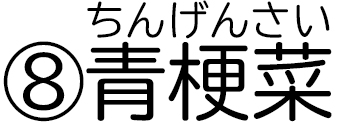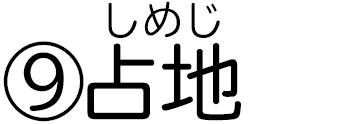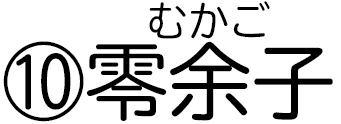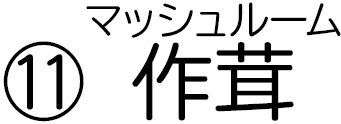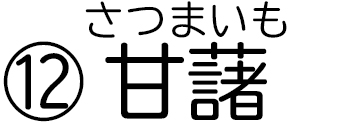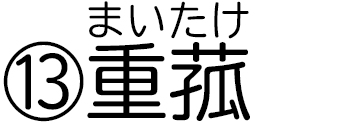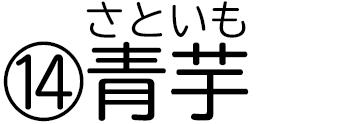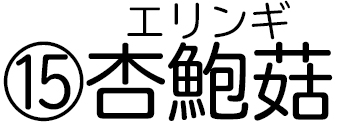少しずつ涼しいと感じる時が増えるこの頃。
季節は秋へと変わってきました。
店先に並ぶ野菜も、そろそろ秋の顔に変わりそうです。
今回は野菜の漢字読み当てクイズの秋バージョンです。
ヒントを頼りに、それぞれの漢字はなんと読むのか当ててみてください。
解答はブログ記事の下部の「解答編を開く」でご紹介します。
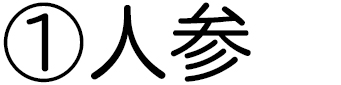
オレンジの甘い野菜。子供は少し苦手な子が多いです。
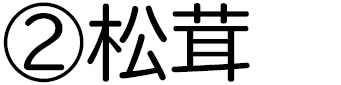
秋の定番高級キノコ。香りは一度嗅いだら忘れられない。
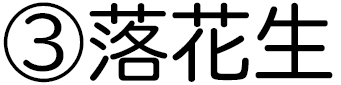
国産は千葉県が有名。木の実に見えますが、実は豆の仲間。
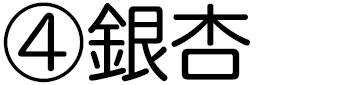
独特の香りが好き嫌いを左右する。街路樹のものが落ちていることもしばしば。

漢字のイメージ通りぬるりとしたゼラチン質が特徴。お味噌汁の具材に。
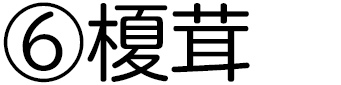
シャキシャキとした食感がたまらない。お鍋に入れたい野菜です。

火を通せばトロトロ、お漬物だとシャキシャキ。色んな食感を楽しめる野菜です。
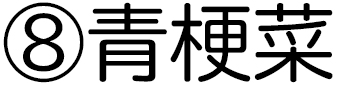
炒め物に最適な青菜。中国野菜の中でも日本に身近な存在です。
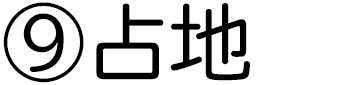
旨味が強く味が良いとされているキノコ。食感も良くてクセになります。
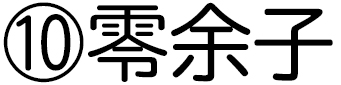
山芋類にできる球体の芽。火を通すとほっくりとします。
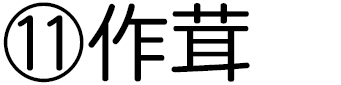
唯一火を通さずに食べることができるキノコ。世界で最も多く食されているのだとか。

食物繊維がたっぷりの野菜。甘みが強いのでお菓子の材料にもよく使われます。
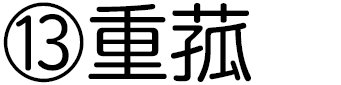
ひらひらとしたヒダが特徴的。きりたんぽ鍋には欠かせません。
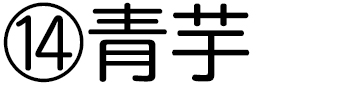
コロコロと沢山実る野菜。子孫繁栄の象徴とされ、お節料理に使われます。

日本には自生しない海外の野菜。加熱するとアワビのような触感になります。
問題は以上です!
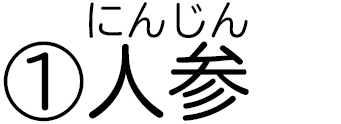
本来は薬草の「朝鮮人参」を表す言葉でした。「枝分かれした根の形が人の姿を思わせた」ことから名づけられたそうです。
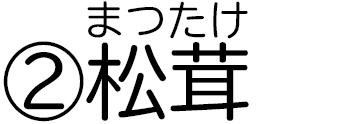
名前の通り「アカマツの根に寄生する菌類」がキノコになったものです。
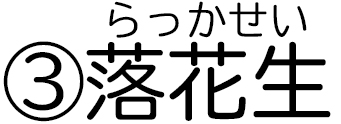
豆類の植物ですが「花が咲いた後に地中に潜って実をつける」ことから名づけられました。
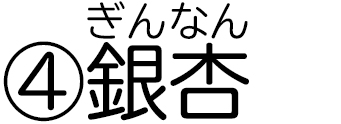
実がなる木の「イチョウ」もこの漢字です。野菜としては「実が白い」ことから名づけられました。
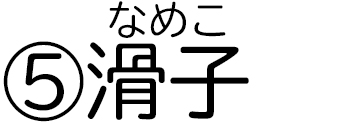
ぬめぬめとした見た目から「滑らっ子(ぬめらっこ)」と呼ばれていたのが後に訛ったといわれています。
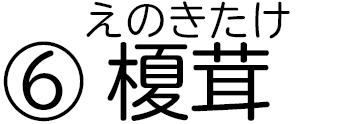
元来の野生の物は「エノキの木から生えたキノコ」です。「榎」という漢字は「夏に日陰を作る樹」という意味の日本で生まれた和製漢字です。

一説には「肥大した根の部分の形が丸くなる」ところから、頭を意味する「かぶり」から由来したといわれています。
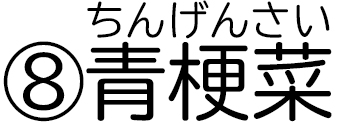
漢字表記は中国のもの。中国語読みで「チンゴンツァイ」と読みます。
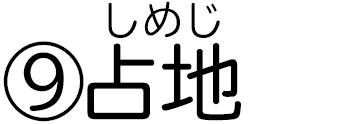
「地を占める」という由来通り「地面を占領するほどたくさん生える」という意味で名付けられました。
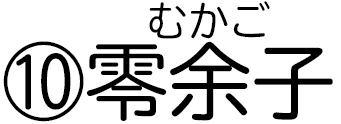
そのままでは読めない熟字訓です。名前の由来は明らかになっていはいませんが「雨のしずくの様にこぼれ落ちる様」から当てられたといわれています。
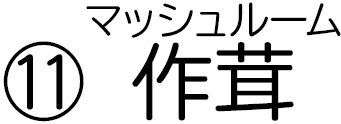
漢字はマッシュルームの和名「ツクリタケ」の表記です。日本に自生しておらず、海外から食用栽培種として輸入されてきました。
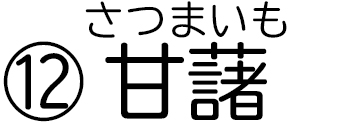
薩摩から日本全国に伝わったといわれるさつまいも。中国では「カンショ」と呼びます。
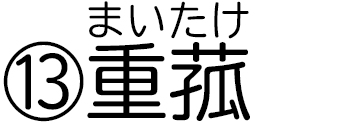
名前は「山で発見すると舞を踊りたくなるほど嬉しい」ことからと言われています。漢字は江戸時代に使われていたもので、なぜこう表記されるのかは不明だそうです。
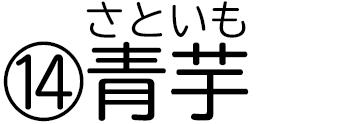
読み方は「えぐいも」で、里芋の子芋専用品種です。名前の通り親芋はえぐみが強いことから名づけられました。
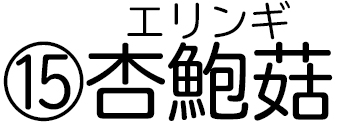
海外にしか自生しておらず、日本では和名がありません。漢字は中国語表記の物で「アワビに食感が似ていて、アンズのように見えるキノコ」といわれています。
秋に旬を迎える野菜は、やはりキノコ類が多めでしたね。
日本の和名が無いものは、お隣の中国語表記がそのまま使われていることもしばしばです。
どの名前も野菜の特徴を押さえていて面白いですね。
次回はどんな漢字が出題されるのか、お楽しみに。